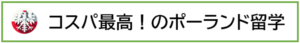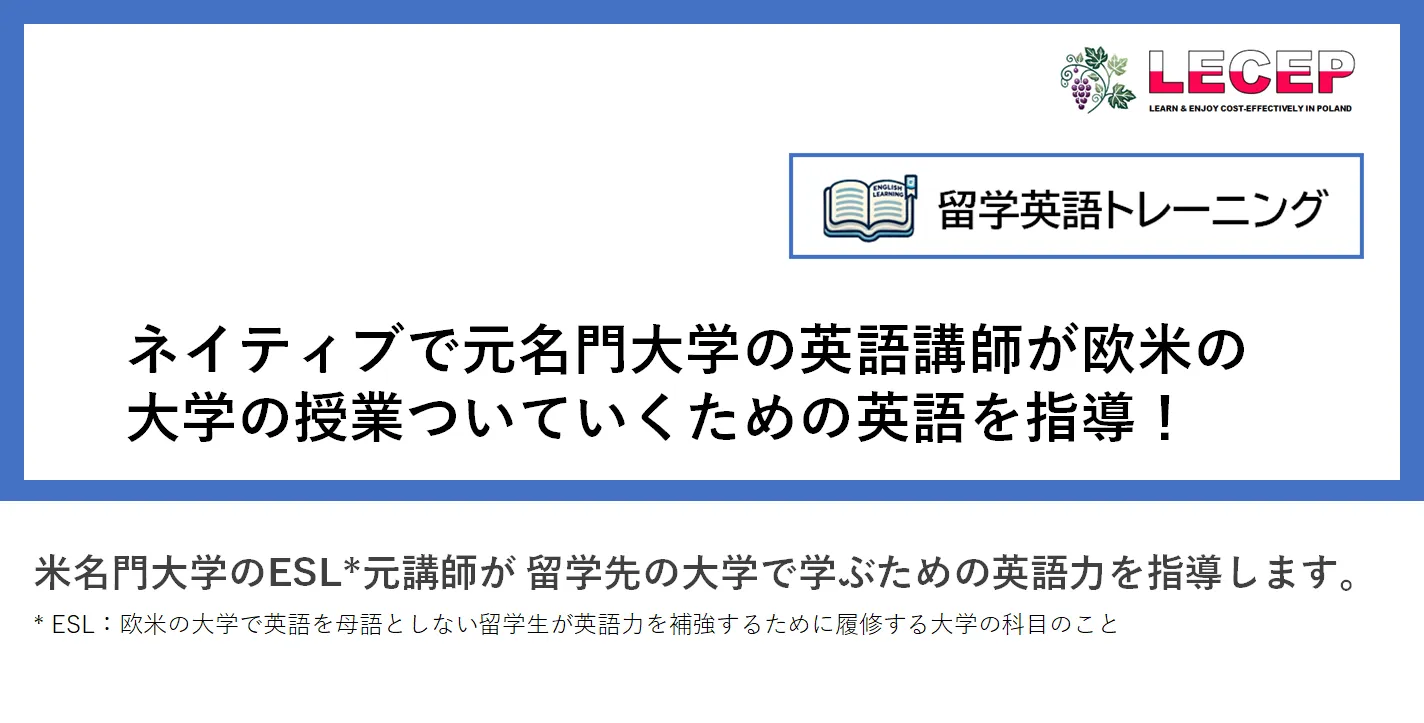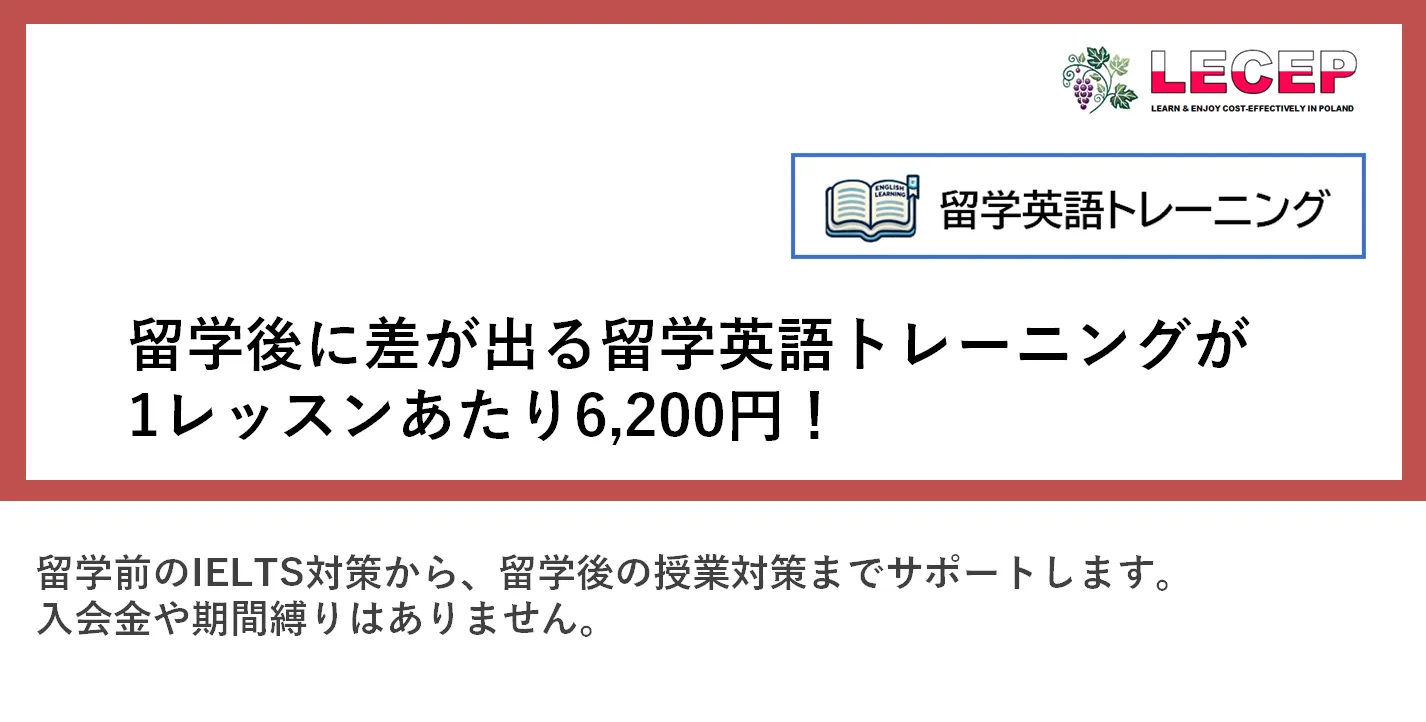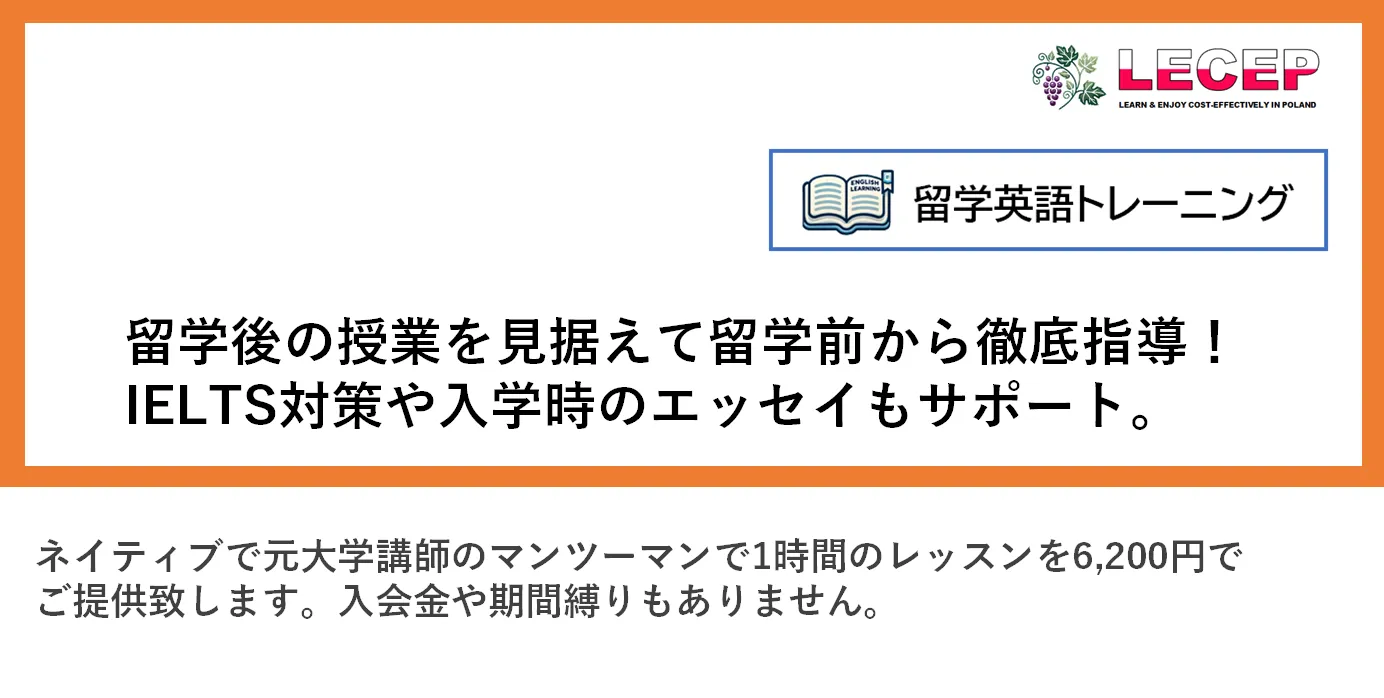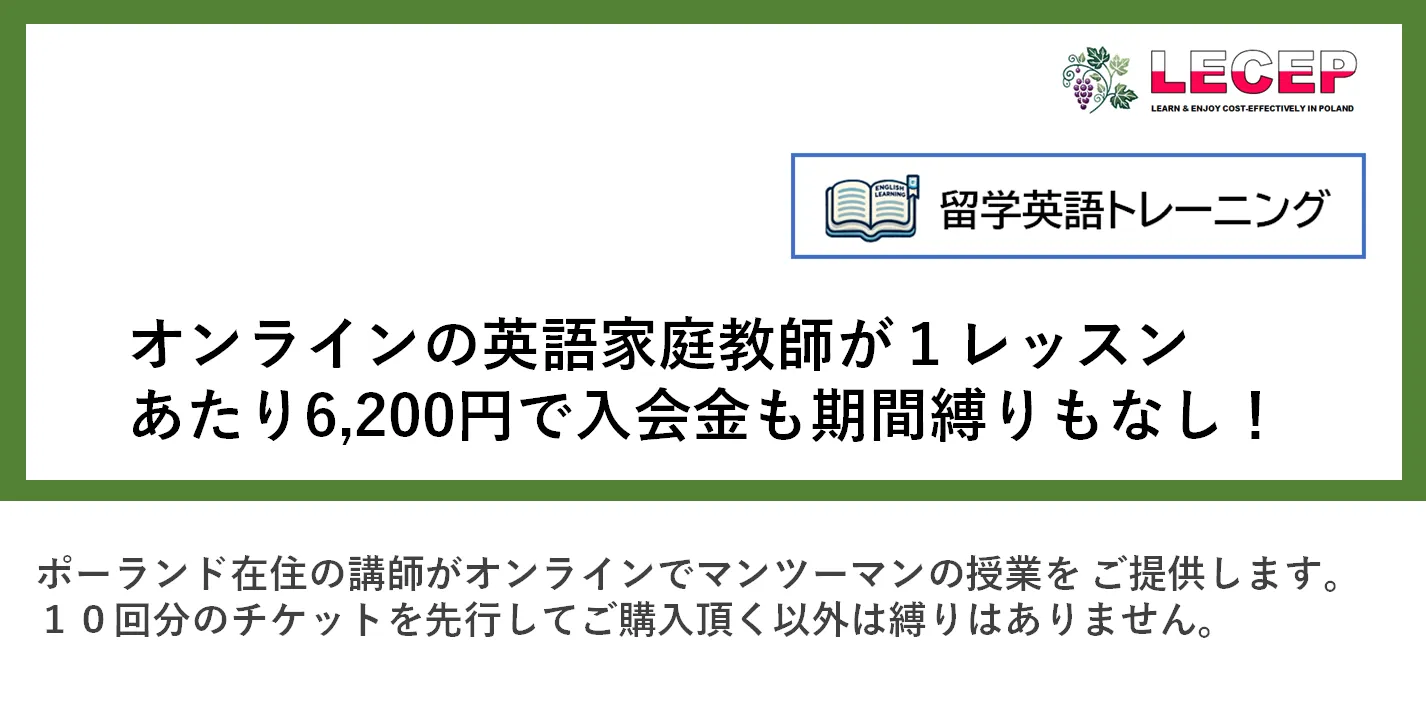〜あらゆるタブーを超えて〜

歴史の壁
留学生活での交友関係で突き当たる最も厄介な壁の一つは恐らく歴史の壁だと思います。正確に言うと歴史に対する認識の違いです。例えば、日本についての知識に乏しい外国人がステレオタイプ的に言う「kamikaze」や「ハラキリ」などで歯痒い思いをすることは、よくある話です。
これを言う外国人にも全員に悪気があるわけではなく、中には日本の歴史に興味があり、もっと知りたい皮切りに「日本ってユニークだよね」というニュアンスで言ってくる人もいます。しかし共通して言えることは、日本の歴史、あるいは文化に対する知識に乏しいことであり、それは日本人である僕達も他の国について言及する時は同じ落とし穴を抱えています。
歴史の話をすることのメリット
歴史に関する話題は非常にセンシティブで、知り合ったばかりでは誰もがなるべく避けたい話でもあります。もし自分の認識と相手の認識の間に齟齬あったらと考えるとそんなリスクは冒したくないのは当然です。しかし、敢えて話すことで得られる利点があります。二つの観点に分けていきましょう。
- 仲を一層深めることができる
- ユーモアに使える
まず一つ目は、実際によくあることです。歴史の話というのは初めは誰もが避けたい話題ではあるものの、最も興味のある話題の一つでもあるかもしれません。
国際交流の場において、あなたは個人として見られるよりも先に日本人として見られることが往々にしてあるはずです。この『日本人』という属性は誰と話すにしても常に大きく付き纏うこととなります。そして海外の人々は『日本人』という属性を歴史、或いはその結果として現れる文化を以て認識するのでこれはお互いを理解する上で重要なプロセスと言えます。
二つ目、歴史の話やセンシティブな話はユーモアになり得ることです。例えば、アングロ文化を中心に大変よく好まれる王道の自虐的ユーモアや皮肉です。
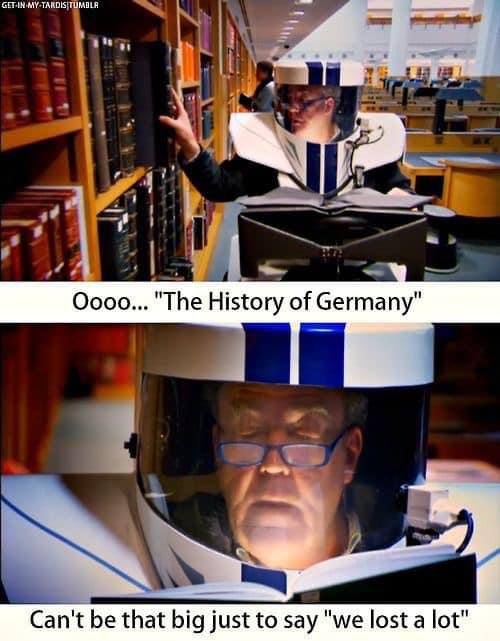
実際をエピソードとしては、授業後にクラスメイト達とアイリッシュパブでビールを飲みに行ったある日の話です。その日は、ビザの問題で強制送還されることになった韓国人クラスメイトの送別会でした。ウクライナ人と韓国人の会話です。
ウクライナ人「ファッキンイリーガルビッチ!(不法滞在野郎!)」
韓国人「お前もビザねぇだろ!」
ウ「顔パス」
この話を少し解説するなら、前提としてウクライナ人はビザを持っていません。なぜならウクライナは現在戦時下で特別にEUが滞在を許可しているからです。また、ウクライナ人は容姿がポーランド人と似ているためよく社会に溶け込んでいます。そんなウクライナ人の彼の言葉は、一見「お前は西洋人ぽくないから強制送還だ」という捉え方もできる話ですが、それも彼らの間柄が許すのです。実際、二人はこのようなことをよく言い合っています。また強制送還を知って、真っ先にこの送別会を提案したのもそのウクライナ人の彼でした。
その一方ではこんな話をしていました。
カザフスタン「俺たちは皆殺しにされるか改宗するかの二択でムスリムになったんだ、お前もそうだろ」
そう言いながらカザフスタン人はメキシコ人の肩に手を回しました。
メキシコ人「よくわかってるじゃねぇか」
これもまた反応に困るブラックジョークですが、一方がイスラム教であるのに対して、もう一方はキリスト教による歴史です。
イスラム教とキリスト教は昔から因縁のある間柄ですが、歴史は時に宗教を超えて友情を育むのだと感じました。
二つの例のように、歴史の話を通じて深まる仲もあるのです。
いうべきことは言った方がいい
もしも誰かが間違った日本への偏見などを言ってきて、自分が不快な思いをした場合、言うべきことはしっかりと言うべきです。
イギリスに住む友人を訪ねた日のこと、家の近くのPUBに連れていってくれました(友人とその友達も連れての三人でだった)。そこには多くの地元客が和気藹々と集まっていて、マンチェスターの郊外にあることもあり、友人はマスターに「日本人は初めてだろ」というと「二人目だ、歓迎するよ」と温かく迎えてくれたのを覚えています。
地元客の一人の陽気なおっちゃんを交えて、ビリヤードを教えてもらったり、ダーツで遊んだりしましたが、全員酔っ払って、色々と制御の効かない時間帯になってきました。
陽気なおっちゃんが僕がダーツで外すと「Kamikazeは良くないぜ」と言ってきたのです。酔っ払っていたのもあり、一度であれば水に流すものですが、何度か言われました。友人は「気にするな」と気にかけてくれたのですがゲーム終了後にテーブルに着いて飲み直しながら話していた時です。
僕「一つ質問があるんだけど良いか」
おっちゃん「いいぜ、なんでも聞いてくれ」
僕「神風は0点だったと思いますか?」
その時、空気が目に見えて変わったのを覚えています。おっちゃんは酔いが覚めたかのように表情から笑顔が消え、たじたじになりながら「俺は日本が好きだぜ、でも悪かったよ」。友人も「こいつ言いよった」とでも言うかのような表情。
こういう時に僕は捻くれているので、『どうせアジア人は言い返してこないとかって思ってたんだろうな』と内心では思っていたのですが、その後、おっちゃんは色々奢ってくれたので万々歳でした。
何より言うべきことが言えて清々しました。
それからは本当に楽しい時間でした。時にはイギリスや日本の歴史の話もしました。
その後の宴は深夜2時過ぎまで続いたのです。
自分が言ってしまう事もある
歴史についての話で不快な思いをさせられることもあれば、逆にさせてしまう事もございます。
その時は、後になって散々後悔するのですが、例えば、今のクラスメイト達と知り合ってまだ仲良くなる最初のことです。
授業の合間に僕は日本の移民についての話をしていました。もっと言うとクルド人問題です。彼らが形上はトルコ国籍で、片道きっぷで日本に居着いて、勝手にコミュニティを作り、事件を起こしたりするから、人々はその地名をクルディスタンからとって『川口スタン』って呼ぶようになったというニュースが当時度々報道されていたのです。
この話をした当時、壊滅的にセンスがないなと感じたのは目の前にトルコ人がいるだけでなく、カザフスタン人がいたことです。
つまり、トルコ人からしたら「クルド人とトルコ人を一緒にして欲しくない」という心情であり、
カザフスタン人からしたら「スタンというのはペルシャ語で国を表す言葉だから『川口スタン』はナンセンス」ということになるのです。
それに気づくのは話を終えた直後でした。幸いにも韓国人の子が「俺たちもそういうこというんだぜ」とフォローを入れてくれたお陰でその場は治りましたが、今でも本当にナンセンスなことを言ったと後悔しています。嫌なやつでした。
落とし穴に引っかからないためには?
このような落とし穴に陥らないために心掛けられることが二つあります。
一つは、常に相手への尊敬を欠かさないこと。特にセンシティブな話題の時はそれを踏まえて慎重に言葉を選ぶ事です。そうすることである程度は回避できます。
二つ目は、相手の歴史を勉強する事です。正しい知識があれば、話す前から相手がどう感じるかを想像することができるでしょう。それだけでなく互いの国のことを知るという喜びを共有できます。
例えば、「Күншығыс елі」これはカザフ語で「太陽の国」即ち日本を指す言葉らしいのですが、日本という名前以外にも、こういう代名詞があることの驚きもあれば「俺はКүншығыс еліから来たんだぜ」とかって話せば「おお、なんで知ってるんだ!?」ともなるのです。
国際交流には様々な問題が付き纏い、時には壁にぶつかることもありますが、それを乗り越えた先に本当の喜びが待ち受けているのではないでしょうか。
時には失敗することもありますが、恐れずにチャレンジし続けることが重要だと思います。