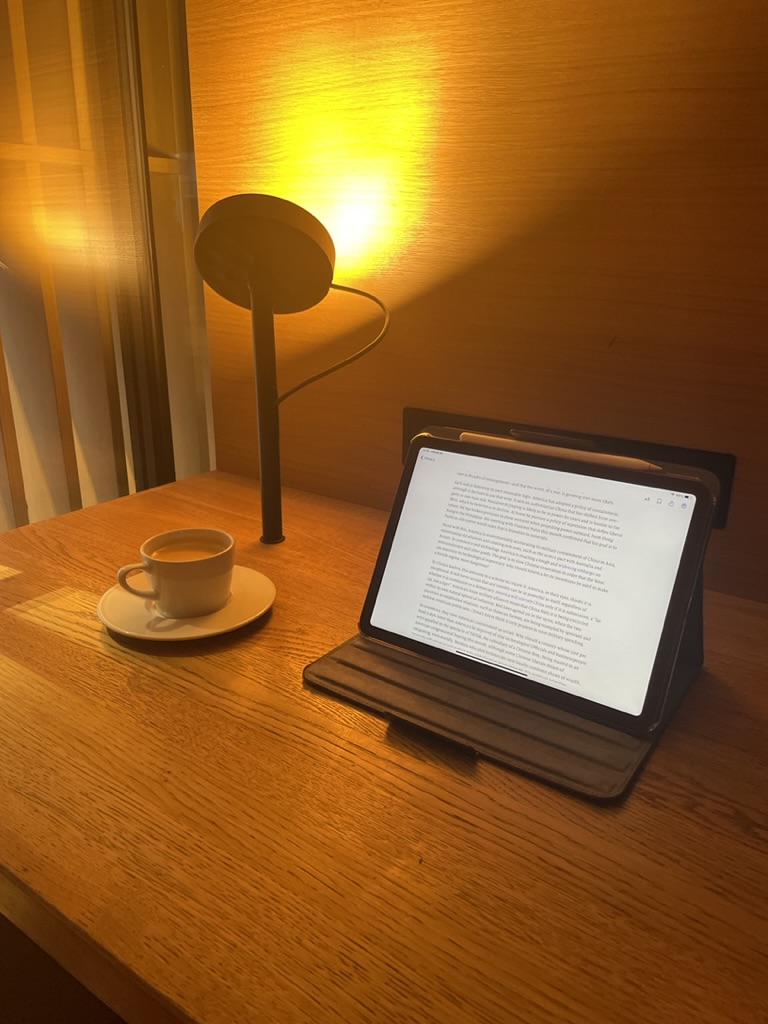こんにちは、息子です。
ヨーロッパの言語はなぜ難解か?
英語圏の子ども達が第一言語としての英語を取得し、扱えるようになる年齢は平均して8歳から12歳だと言われています。それに対してポーランド語は15歳前後。僕は大学で1年間ポーランド語の授業を取りましたが、最終試験で渋い顔をしながら合格点をくれた先生に言われたのは「君のポーランド語の文法力はUNDERGROUNDレベル」でした。結論づけてしまえば、僕は全くこの言語に馴染むことができませんでした。
日本語を扱っていると、言葉と文字の間にかなり厳密で合理的な関係があると思うことがあります。現代日本語の原型はひらがな、カタカナであり、「い」、「ろ」、「は」という個別の音節を持った文字がありそれらを組み合わせることで単語となり、文章となります。それがそのまま音になるので、それを理解すれば小さい子でも日本語を聞いて文章に起こすことに困ることはなかったでしょう。
以前、大学の同回生に日本語を教えて欲しいと言われて、授業後にノートを使いながら説明したことがあります。すると「これはかなり合理的な言語体系ね」と直ぐに理解したようで、僕がさ行までを『ひらがな』で書き下すと、すかさず「これが好きなんだよ」と言いながら『さけ(酒)』と書き返されました。ここで強調したいのは同回生の物分かりが良いという自慢ではなく、日本語という言語体系の持つ合理性です。
思うに、ヨーロッパの言語ではそうはいかないはずです。フランス語が典型的ですが、書いた文字と実際に話している事の間にかなりの乖離が認められるはずです。フランス語も文献によると、17世紀までは語尾を発音せずに落とすという事をしていなかったそうですが、それ以外の言語をとっても、文字単体に与えられた音と実際にそれを使った単語の発音が如何にかけ離れたものかは想像に難くないと思います。
このような違いが生まれた理由を考えると、恐らく、ラテン文字を使う現在のヨーロッパの言語は一部を除いて翻字された言語体系だからでしょう。翻字というのは、まず口語があり、他の言語体系から輸入した文字を口語の発音に当てはめることを言いますが、イタリア語のような一部のラテン系長女格言語を除くヨーロッパの言語は翻字をするために、元あったラテン語の21文字に特殊な文字を足しただけでなく、組み合わせによって特殊な発音をするように、即ち文字単体の発音と単語としての発音の間に乖離が生まれたのです。
これらの祖となる古ラテン語ですが、これは日本語と同じく、多くの古代語の特徴を備えております。例えば、伸ばし棒「ー」の要素を持っていたり、冠詞がない、主語を省略でき、語順が自由などなど。
文字単体の発音と、単語や文章としての発音に乖離もなく、ローマ字のように読めるため、面白いことに、実は、日本人はラテン語の発音に関してはヨーロッパの人々と比べても上手なのです。特に伸ばし棒に関しては、現代のヨーロッパ系の言語にはもはや存在しない要素なので、彼らがラテン語を正しく発音しようとすると、特殊な訓練が必要となるようです。
最も、英語に関しては「サムライイングリッシュ」と揶揄されるほどですが?
ポーランド語の難解さ
ポーランド語はこの翻字されたヨーロッパ言語の最たる例の一つではないでしょうか。ポーランド語はスラブ系の言語に属し、ロシア語、ウクライナ語と同系統の言語です。しかし、ギリシャ文字を原型に改良したキリル文字を使うロシア語やウクライナ語とは違って、ラテン文字を用います。しかし、ラテン文字をポーランド語の発音に翻字するために、特殊文字を含め、アルファベットの文字数は32文字となっています。一般的に、ラテン語から遠くなり、母音と子音が多くなるほどアルファベットの文字数が増えていく感覚です。

またポーランド語はラテン語と同じく主語を省略するので、それにって生まれる豊富な格変化の型など、チャレンジャーに学ぶことを躊躇わせる要素がとても多いのです。
スラブ系の言語も外部から文字を輸入していますが、ギリシア系を使うか、ラテン系を使うか、この両者の違いは宗教的、歴史的背景によって生まれました。
ここで話はだいぶ遡りますが、古代ローマ帝国が東西に分裂した時に、西ローマ帝国はラテン語が用いられ、東ローマ帝国(今でいうトルコのイスタンブールを首都とした)の地域では、元々からギリシア語が広く一般的に使われていたため、ギリシア語が公用語として使用されました。
その後、西ローマ帝国は間も無くして滅び、その遺産としてローマンカトリックを残しますが、一方東ローマ帝国はその後も国としての体制を維持し続け、東方正教会の潮流を生み出しました。文字が輸入されるということは往々にして宗教が輸入されるということとイコールです。なぜなら、宗教の教えは聖書(バイブル)によって広められますが、文字の普及なしにはその目的が達成できないからです。このような理由により、ローマンカトリックの国はラテン文字を使い、東方正教会の国々はギリシア文字を用いることなります。今から約1000年前にビザンツ帝国によって東方正教会と共にギリシア文字がロシア、ウクライナに入ってきました。
時を少しおき、ポーランドにカトリックと共にラテン文字がもたらされます。このように歴史が複雑に織りなした結果として、同じスラヴ語であっても、異なる文字を用いるようになりました。
ところが、言葉は文字を超えます。実際にポーランドとウクライナでは文字が異なりますが、語彙の三割程度が似ているため、互いに共通言語を持たずとも、翻訳なしに意思疎通ができると言います。孤立した言語体系を持つ、我々日本人からしたら理解のしづらい話ではございますが。