
ヨーロッパの文明に触れていると常々思うのは、やはり西洋文明の基盤は古代ローマにあるということです。
18世紀の歴史学者エドワード・ギボン、彼の著書『ローマ帝国衰亡史』はあまりにも有名ですが、その核心が移民問題であったことは多くの人にとって覚えておくと良い事柄ではないでしょうか。
多くの先進国が抱える移民問題というのは、何も現代特有のものというわけでもないのです。現在多くの移民と悩みを抱えるドイツやイギリスなどのゲルマン人と呼ばれる人々、2000年前には彼らこそが古代ローマ帝国を悩ませる移民であったのですから。
移民とは?
一般的に『移民』の定義としては国際移住機関(IOM)によるものが理解されています。
『「移民」とは国際法などで定義されているものではなく、一国内か国境を越えるか、一時的か恒久的かに関わらず、またさまざまな理由により、本来の住居地を離れて移動する人という一般的な理解に基づく総称です。』
つまり、移民という単語自体がかなり広義的で、労働目的で移住してくる人や、僕のような留学生、不法滞在者まで全ての移民を一括りに指す言葉です。
ですから、一般的に、こういう広義的な言葉を使うときは大変な注意が必要です。
ある日、授業終わりにクラスメイト達と飲みに行った時、ポーランド人の一人が「これからやることがある」と途中で抜けていきました。すると、入れ替わりでやってきたドイツ人が「あいつなら、さっき移民反対のデモで見かけたよ」って言って場が変な空気に包まれたのを覚えています。
「さっきまで留学生達と楽しく飲んでたのに?」
彼がデモに参加していたのは、単に不法移民反対という意図なのですが、移民という言葉を一緒くたに使ってしまうと誤解が生まれやすいのも事実です。
移民=悪というイメージが強いですが、そう判断するには様々な角度から見ておくことが重要です。移民のもたらす利益不利益は当然ありますから。
今回は、技能の良し悪し関係なく、労働目的でやってくる移民を焦点に当てて書いていこうかと思います。
移民を受け入れるメリット
移民を受け入れることのメリットは大きく分けて二つあります。
- 経済的側面
- 少子化の緩和
まず、経済的側面ですが、これは移民というのは純粋な労働力であり、消費活動、納税をする経済主体であるわけです。純粋に人口が増えることによって経済も活性化し、所謂 “Immigration Surplus” という経済効果をもたらします。米国の場合、それでも現地民に還元される割合は0.2% 〜 0.4%くらいだそうですが(引用元)、国単位で見たときには絶対的なプラスになるわけです。
また、高齢化社会と人口減少に対する解決策としても有効です。
例えば、特殊合計出生率を比較してみると
こうしてみると移民による功労は一目瞭然であることがわかります。
そして何よりも、民族や人種を超えた絆は美しい。
ある日、旅行でパリを訪れたとき、
白人のおばあちゃんと、5歳くらいの肌色の違う子供が手を繋いで歩いていました。
きっとおばあちゃんとお孫さんに違いない!なんて素敵な絆なのだろうと感じたことを覚えています。
移民を受け入れるデメリット
メリットもあればデメリットもございます。しかし、ネット上や一般的に多く言われる治安や社会的分断の問題は、昨今、強調される傾向が強く、定量的に把握できないため、議論しません。今回は、公共サービス一点に焦点を当てます。
イギリス、マンチェスターに住む友人を訪れた時、移民についての話題が少しでました。僕にとってその時が、初めてのイギリス旅行、街中は想像以上に多民族的で、警部補として仕事している友人の意見を聞いてみたかったのです。
「なぜイギリスにはこんなに移民が多いのか?」という問いに
「俺たちの社会保障が目当てだと思ってる。俺たちには無料の家、無料の食べ物、生活保護、医療全て揃ってるからな」と言っていました。
実際これは当時の僕にとって新しい視点です。移民問題というのは往々にして犯罪や治安、文化的侵食が強調されがちですが、財政負担にもなり得るのです。
イギリスにおける低所得移民に対する公共サービス負担は一人当たり£3000(2025年で約60万円)の赤字だと算出されています。
ちなみに「経験上、移民と自国民のどちらが犯罪が多いか?」という問いに対しては特に関係ないと思っているそうです。
移民は受け入れるべき?
世の中には結論を急ぎたがる人も一定数いるようですが、冒頭でも述べた通り、人類の長くて短い歴史の中で一度も答えの出たことのない問題にそう簡単に答えを与えられるはずがありません。
個人的には、部分的に僕を含めた、日本のデザインされたレールの上を歩くだけの子供達は、比較的発展途上の国からきて気骨とエネルギーに満ち溢れた子供達に太刀打ち出来ないと考えています(能力が同じな場合に限られますが)。


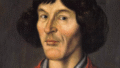

コメント